2022年5月、ミニ冊子「すべての食品にトレーサビリティを~法制化の必要性」を発行しました。ミニ冊子「ゲノム編集食品が食卓へ~表示とトレーサビリティの必要性~」に続き、ミニ冊子シリーズの2冊目となります。
日本にも、食品全般に基礎的なトレーサビリティを義務付ける新しい法制度が必要です。トレーサビリティが法制化(義務化)されれば、記録に基づいて表示の正しさの検証が確実にできるので、遺伝子組み換え食品の表示制度が見直され、ゲノム編集食品の表示義務化の一歩となります。また、生産段階における環境への配慮への監視を通じて持続可能な食と農の実現につながります。
本書作成にあたり、食品トレーサビリティの推進に向けた各種事業に取り組んでいる一般社団法人食品需給研究センターの方を招いて学習会を行いました。また、トレーサビリティを自主的に実践している企業として、石井食品株式会社及びマルハニチロ株式会社にご協力いただきました。ページ後半に2社への取材報告を掲載しています。
ミニ冊子「すべての食品にトレーサビリティを~法制化の必要性」チラシ
たねと食とひと@フォーラム冊子紹介22.10.6
既刊冊子案内ページ
たねと食とひと@フォーラム事務局宛、Email:info@nongmseed.jp又はFAX:03-6869-7204 でお申込みください。
★6月11日(土)にはミニ冊子出版記念オンライン学習会「すべての食品にトレーサビ
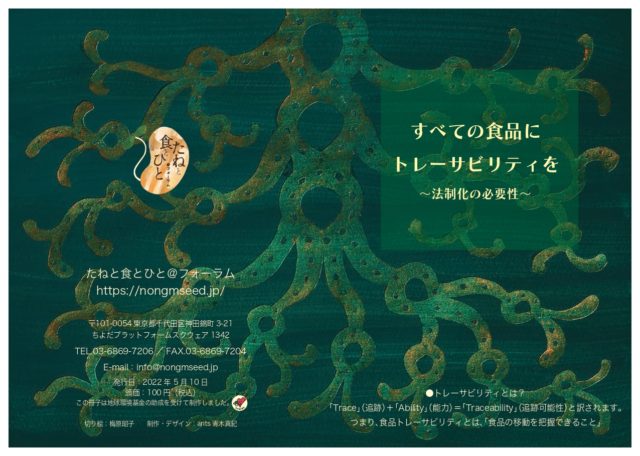 ミニ冊子「すべての食品にトレーサビリティを~法制化の必要性」
ミニ冊子「すべての食品にトレーサビリティを~法制化の必要性」
目次
トレーサビリティってなあに?
なぜトレーサビリティが必要なのか?
あったらよかったのに・・
食品トレーサビリティの法制度比較
日本の食品事業者における基礎的なトレーサビリティの現状
より高度なトレーサビリティを自主的に実践している企業の方に聞きました。
石井食品株式会社・マルハニチロ株式会社
私たちの提案
発行日:2022年5月10日
頒 価:100円(税込)
イラスト:梅原昭子
制作・デザイン:ants 青木真紀
本書制作にあたり参考にした資料
食品事業者における食品(畜産加工品と水産加工品)トレーサビリティの取り組み状況アンケート調査結果(2020年12月)
この冊子は地球環境基金の助成を受けて制作しました。![]()
より高度なトレーサビリティを自主的に実践している石井食品株式会社とマルハニチロ株式会社にアンケートを実施しました。
1.トレーサビリティを導入された理由、きっかけ、時期はいつでしょうか
石井食品:2001年の牛海綿状脳症(BSE)がきっかけで、食品偽装事件や事故が相次ぎお客様からの問い合わせが倍増しました。2002年から全商品を全面開示しました。基本方針として3大原則「無添加調理、厳選素材、品質保証番号」のコーポレート・アイデンティティを掲げています。トレーサビリティはその延長線上にあります。工場では2000年から2次元バーコードの管理を行い、お取引先様向けに開示しました。お客様に向けては、履歴情報を遡及できる「OPEN ISHII」という情報公開システムができました。正しく伝えられるひとつのツールと考えています。正直に答えることができることは、社員の自信にもつながっています。
マルハニチロ:食品の回収が必要となる事件・事故が起こった場合、問題のある製品を素早く回収することが求められます。その際に問題のある製品の生産・加工から流通販売過程の食品の移動(使用した原材料や製品の出荷先など)が特定できなければ、原因究明が難航し回収対象を絞り込むことが困難となってしまいます。食品の移動を把握できるトレーサビリティは、消費者の信頼を確かなものとする上で重要であり、また、食品の安全性に関して不測の事態が発生した際の原因究明や被害の拡大防止などに有効であることから 2000 年に導入しました。
2.導入までの過程で、費用面、書面作成など、いちばんご苦労されたことは何でしょう
石井食品:原材料の履歴情報など、お取引先様から詳細情報を集めることが一番困難でした。「なぜ全部開示しなければならないのか」と履歴情報を開示していただけない業者との取引はなくなりました。コンビニをはじめとする取引が減り、大幅な減収となりましたが商品価格を値上げするということはしませんでした。
マルハニチロ:特に社外の委託製造工場に対して、新たな手間をなるべく生まずに済むように配慮しながら要請・指導することでした。
3.トレーサビリティ導入後の課題は何でしょうか
石井食品:社内の意識改革。3大原則「無添加調理、厳選素材、品質保証番号」を貫くために、営業面でもお取引先様に理解いただくことや工場においても厳密な管理が要求されることなどです。
マルハニチロ:水産原料などには1つのロット(数量)が大きなものもあります。ロットの大きい原料に問題があった場合は、その原料を使用した製品の対象範囲が大きくなってしまうことが課題です。
4.トレーサビリティを導入している商品名と具体的なトレーサビリティの流れをお教えください
石井食品:全商品を対象としています。
マルハニチロ:当社が初めてトレーサビリティを導入した商品は海外産の冷凍枝豆です。冷凍枝豆の場合、原料となる枝豆を専用農場で肥培管理を一元化し、農薬使用条件などの完全サポート体制を構築しております。枝豆の収穫前後には残留農薬の自主検査を徹底し、商品パッケージにロット番号を印字し、データベースによる管理を可能とすることで栽培・加工・包装・出荷日などの記録を確認できる体制を構築しています。専用農場での一括管理(農薬管理、検査)を徹底→工場では商品パッケージへトレーサビリティ管理の情報(ロット番号)記載→消費者様はロット番号よりトレーサビリティ情報の入手が可能。
5.これまで、どのような場面でトレーサビリティをお使いになりましたか
石井食品:事故品が発生した時。大きな事故を防げていることと、近年お問い合わせで増えているアレルギー対応に役立っています。
マルハニチロ:消費者様からの問い合わせ対応(国内で無認可の添加物使用の有無など)や食品の回収が必要となる事故が起こった場合の対応。
6.トレーサビリティの導入が難しい商品について、理由と課題は何でしょうか
石井食品:お取引先様に情報を開示してもらえない場合は取引を行っていません。
マルハニチロ:トレーサビリティ導入が難しい商品はないと思いますが、課題は取り扱い製品の種類が増えることで使用する原材料も増え多岐に亘り、全てのトレーサビリティ情報を管理することが煩雑となることです。
7.すべての食品へのトレーサビリティの法制化(義務化)について、どのようにお考えでしょうか
石井食品:顧客に正しく伝わることが最も大切と考えているため、「正しくわかりやすく伝わる仕組み」を大切にしていきます。その中で法制化があるのであれば反対するものではありません。
マルハニチロ:全ての商品へのトレーサビリティ実施の効果は問題発生時の被害や損失を小さくする等のリスク管理の強化に加え、製品の品質向上、顧客満足度や企業の信頼性の向上にもつながり、食品事業者にとっては有効な手段となります。一方、全ての商品への義務化によりコストが増大します。そのコストを食品事業者のみが背負うことがないようご配慮いただきたいと考えます。コストと効果のバランスを考慮して頂き食品事業者が継続的に実行できることで、トレーサビリティが浸透し定着することを望みます。
以上
<石井食品株式会社を訪問しました>
3月16日(金)、ミートボールでおなじみの石井食品(株)を訪問し、執行役員の池田明子さん、広報チームの市川菜緒子さんからお話を伺いました。
船橋駅から徒歩数分、三番瀬に程近い本社の1階は、直売所の奥にカフェ、キッチン、キッズスペース等を備えた素敵なコミュニティハウスにしつらえてありました。食と健康、食育に関する資料や、地域の方々の手作り小物が並ぶコーナーもあり、会社の姿勢が伝わってくるようで好感が持てました。
戦後1946年の佃煮製造から始まった石井食品が、看板商品となったミートボールの発売を開始したのは1974年だったそうです。2000年から「無添加調理」「厳選素材」へと舵を切り、全工場にて「品質保証番号」を取り入れたとのこと。現在もこれらが三大原則としてコーポレート・アイデンティティ(基本方針・社是)になっているそうです。
「納品いただく全てのお取引先様に、原材料、調味料等の詳しい情報をオープンにしていただくようにお願いし、開示してもらえない業者との取引は停止しました。その結果、商品のラインナップが絞られ、年間売上が大きく減少した時期もありました」との歴史には驚きました。
今では、商品一つひとつに印字された品質保証番号から、「OPEN ISHII」というホームページ上のサイトで、全商品の情報が公開されています。履歴管理(トレーサビリティ)が徹底しているため、何かあっても早く確実に対処できるし、近年増えているアレルギーのある方からの問合せにもきちんと対応できるそうです。
振り返ってみれば、納入業者とのお付き合いや社内の意識改革には困難もあったが、やり抜くことでお互いを信頼できる関係を築くことができたといいます。また、情報を正しく分かりやすく公開することで、顧客との信頼関係づくりにもつながった手応えがあるそうです。品質管理の取り組みは、働く社員の誇りや自信、モチベーションの源泉ですとのお話に、一同、感銘を受けました。
以上